こんにちは。
本店の垣崎です。
結婚式でのご祝儀や、お葬式での御香典を包むために使われる「袱紗(ふくさ)」、皆さんお持ちでしょうか。
袱紗に包んで渡すのは知っているけれど、袱紗の色や包み方、形の選び方などなんとなくしか知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私も友人の結婚式で袱紗を使用する機会があり、包むのは知っているけれど、どうやって渡すのかな?と思い調べたことがあります。
初めになぜ袱紗に包んで渡すのかというと、結婚式でのご祝儀やお葬式での御香典をかばんに入れて持ち歩く際、しわがついたり、水引が崩れたりすることを防ぐ目的があります。
また、熨斗袋で金封し、さらに袱紗で包むことによって、礼節や、相手と嬉しさや悲しさを共有するという気遣いを示すことができるからです。
袱紗は色もたくさんあり迷います。
目的によって色が違うので注意が必要です。
一般的には下のように言われています。
慶事用・・・紫、赤、朱、オレンジ、黄色、薄紫、ピンクなどの暖色系
弔事用・・・紫、緑、紺、藍、茶色、グレーなどの寒色系

目的によって色を変え2つ持っておくか。
どちらにも使用できる紫を1つ持っていると便利です。
袱紗の形は、大きく分けて「包むタイプ」と「挟むタイプ」の2つに分けられます。
「包むタイプ」には、正方形の布がそのまま使われた風呂敷タイプ、それに金具が付いた爪付きタイプ、台付きタイプがあります。
台と爪がどちらもついているタイプもあります。

挟むタイプには、金封袱紗というものがあります。
中にそのまま挟むだけでよいので、開閉がとても簡単です。
最近では、使いやすさの面から金封封鎖は老若男女問わず人気です。
そして渡し方ですが、袱紗で金封を包む時の重要なポイントは、慶事の際は袱紗を右開き(左手で持って右手で開けられるよう)に、弔事の際は袱紗を左開きにすることです。
慶事の場合は、自分から見て右開きになるように持ったら、袱紗から金封を取り出して袱紗の上に置きます。
時計回りにまわし、相手が文字を読める方向で渡します。渡す際にはお祝いの言葉を一言。
※弔事の場合は右と左を置き換え、反時計回りにして渡します。渡す際にはお悔みの一言を添えましょう。
大人のマナーとして、お子さんが独り立ちするときや、成人祝いにプレゼントするのもいいかもしれませんね。







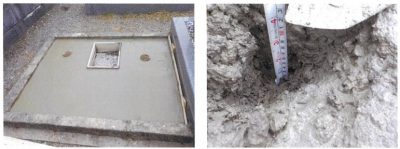
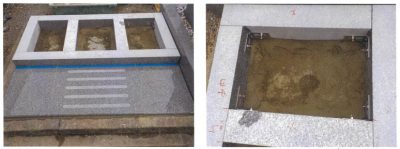



-150x150.jpg)
-1-150x150.jpg)



















































