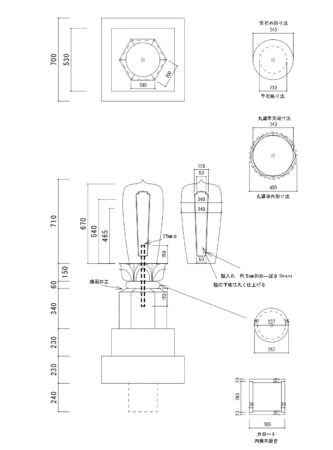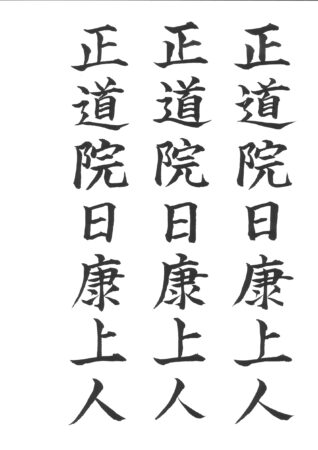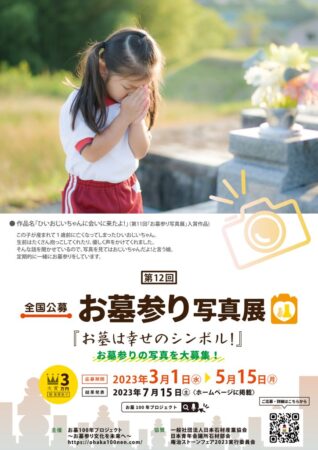こんにちは。本店スタッフです。
先日、葬祭部の方から「納棺師さんに来てもらってメイクや着替えを習うんだけど見てみない?」と情報を頂いたので参加してきました。
大きなメイクボックスには化粧品以外にお顔の修復に使われる薬品や注射器なども入っています。すごい…。営業さんや現場の方の道具箱もそうですが、仕事道具が詰まったバッグは本当にかっこいいですね。

モデルは葬祭部の板垣さん。目の上にある傷を消していきます。まず肌色のワックスで傷部分をカバーした後、真っ赤なパウダーで周りの肌色と馴染ませていくと…見事に傷が消えました。
ただお化粧をするだけではなく、こういったキレイに見せる技も使われるのです。

みなさんも家ではばっちり決まっていたメイクが出先のトイレで鏡を見たらなんだか浮いてる!?と、ビックリとした経験はありませんか?
エンゼルメイクも同じで、お化粧を施した場所と葬儀会場の照明が違うと色の見え方が変わり「あれ?」となってしまうそうです。そういったところも想定しておられます。
次はお着せ替えです。着物とスーツを習います。

いわゆる死に装束というのも最近は白帷子だけではなく生前着られていたお気に入りの服やエンディングドレスなどを選択肢が増えています。播州織でエンディングドレスを作られている会社もありますね。
じゃあ、私は若い頃好きだったロリータ服を… と思いましたが、嵩張るしパーツも多いので着せていただくのはちょっと無理かもしれません。このように、どうしても着せるのが難しい場合は白帷子に着替えたのち上からお洋服を掛けるという方法もあります。
仕上がった際のお袖の角度まで気を配ります。


今度は男性スタッフに交代。コツをつかめば誰でもラクラクできるよ!というものではありません。
どんなに大変でも「重たいなー」「よっこらしょ」なんて雰囲気は絶対に出せません。常に涼しい顔でスッとこなしていかなくてはいけない、本当に素晴らしいお仕事です。
…ということで、ド素人の私はただただ感動するばかりでした。
納棺師という職業は以前から興味があり、今回お話を聞いていて更に憧れが強くなりました。現実は、超ド級のあがり症なので人前に立つお仕事は無理なのですが…(涙)
そんな私でも実践できそうだなぁと思ったのが「美しい所作は指先から」というアドバイスです。
納棺師の方は、日頃からすべての動作を美しく行うように心がけているとのこと。例えば、ゴミ袋の口を結ぶ時でも美しく…洗濯物を干す時でも美しく…。
これは今後実行してみたいと思いました。