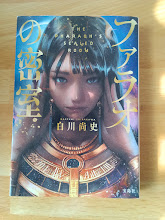いつもお世話になっております。堂本です。
梅雨が短く、瞬く間に猛暑となり暑さにうな垂れる毎日となってまいりました。
皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
先日、人生で初めて、私が担当致しましたお墓が完成し開眼供養のお手伝いに行ってまいりました。
自分でもこのような機会に恵まれるとは幼いころの自分は思ってもみなかったと思います。
初めての建立ですのでお墓ができていく様子をその都度、見に行っておりまして、何もない場所に基礎が敷かれ

徐々に、形となり統一感を持ってお墓に成っていく行く様は、一つの儀礼のようにも感じられます。

施主様から良いお墓ができた、とのお言葉を頂き、ほっ、と胸をなでおろしました。
墓石の建立に限らず、霊標への戒名の彫刻や、リフォーム、お墓じまいなどの打ち合わせの際に、施主様からは様々な思いや歴史を聞かせていただきます。
そのようなやり取りの中で少しでも、施主様やご先祖様の思いを形にできればとの思いは話を聞けば聞くほど強くなってまいります。
お墓とは、単に石の塊ではなく、様々な思いや歴史が形になったものだと今回改めて強く思う機会でした。
もし私がご担当させていただく際はぜひたくさんのお話をお聞かせください。
「人」が様々な出来事を通して「仏」と「成って」、「成仏」と言うように、「石」というものが「人の思い」を経てお墓に「成る」というのを感じることができる機会でした。
このような機会に出会わせていただきありがとうございました、と、言葉が心から浮かんでくるような出来事でした。
今後とも、少しでも、施主様の思いを形にできるように励んでいきたいと思いますので宜しくお願い致します。




-400x398.jpg)
-400x380.jpg)