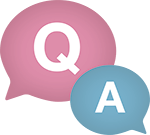こんにちは
滝野店スタッフです。
今年の梅雨開けは早かったですね。
例年より3週間ほど早くて、シトシトと雨が降った記憶があまりありません。
楽しみにしていた紫陽花も今年は見に行けなかったです。
紫陽花といえばアジサイ寺というのもあるほどよくお寺で見かけますが、
なぜお寺に紫陽花が多く植えられているのでしょうか?
諸説ありますが、
*亡くなった人を弔う花として、お寺に植えられた
「四葩(よひら・花弁が4枚ある)」の別名をもつ紫陽花が、
昔は「死(し)」を連想させる花とされていたそうで、
そのためお寺では紫陽花を多く植え、死者に手向けて弔ったという説。
梅雨の季節は、気温の変化が激しく体調を崩しがちで、
医療技術が発達していない時代は流行り病として死にいたるケースも多くありました。
その際に、紫陽花は仏花として簡単に手に入れることができ、
亡くなった方を弔う形として、紫陽花を育てるお寺が増えたといわれています。
紫陽花は雨に打たれるほど美しく咲くと言われます。
大切なかたを失った悲しみの涙と雨が重なったのかも知れませんね。
*紫陽花の花言葉「無常」が「諸行無常」につながる
紫陽花の花言葉の一つに「無常」があり、仏教の「諸行無常」の教えを感じさせる説。
正岡子規の俳句に
「紫陽花や きのふの誠 けふの嘘」
というのがあります。
諸行無常と仏教では言いますが、昨日まことだと思っていたことが、
今日はウソになってしまうことを紫陽花の花に例えた歌です。
*寺がある場所が山の中で、紫陽花との相性が良かった
寺は山中に建てられることも多く、日差しが強すぎず土地が程よく湿っているのが、
紫陽花が育ちやすい環境だったという説。
紫陽花は手間をあまりかけなくても育つので、
手入れをしなくても寺の中が荒れるということもありませんでした。
なるほど、たまたま自生していたわけではなかったのですね。
お寺の厳かな雰囲気と、紫陽花の慎ましいすがたがよく合いますね。
来年は出来るだけたくさん見に行きたいと思います。